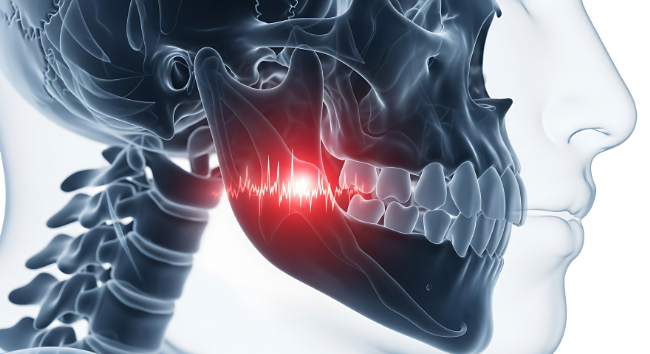こんにちは。兵庫県西宮市にある医療法人社団 西宮北口ライフ歯科・矯正歯科・小児歯科です。
顎関節症とは、顎の関節や筋肉に障害が生じることで、口を開けにくくなったり、カクカク音が鳴ったり、痛みが生じたりする病気です。この病気に悩まされている方は少なくありません。
顎関節症は、ストレスや噛み癖、生活習慣など、さまざまな要因によって引き起こされますが、中でも歯並びや噛み合わせが関係しているのではないかと心配される方も多いのではないでしょうか。
今回は、歯並びの悪さと、顎関節症との関連について解説します。
目次
顎関節症とは
顎関節症は、顎関節やその周囲の筋肉、靭帯などに異常が生じることで発症します。日本人の約5人に1人が顎関節症を経験するといわれており、特に女性に多く見られる傾向があります。
顎の関節は、口を開けるとき・閉じるときに動いており、日常生活において常に使われています。そのため、何らかのトラブルが生じると、食事や会話などに大きな影響を及ぼします。
顎関節症は決して珍しい病気ではありませんが、軽視されやすいのも特徴です。ただの痛み、一時的な不調と考える方が多く、症状が悪化するケースも珍しくありません。
しかし、適切に診断・治療を受けることで、早期に改善できます。顎関節症を理解し、自分自身の症状を正しく把握することが、治療の第一歩です。
顎関節症の主な症状
顎関節症では、次のような症状が現れます。
- あごを動かすと音がする(クリック音など)
- あごが開けにくい、開かない
- あごの痛みやこわばり
- 食べ物を噛むときの違和感
- 顔や耳周辺の痛みや違和感
症状が軽度であればゆっくりあごを動かす運動をする、ご自身で温めるなどの簡単な対処法で症状が和らぐこともあります。その一方で、症状が重症化している場合、深刻な事態を招く恐れもあるため注意が必要です。
歯並びが悪いと顎関節症になる?
結論から言えば、歯並びの悪さそのものが顎関節症の直接的な原因になるとは限りません。
しかし、上下の歯が正しく噛み合わない状態が続くと、あごの使い方に偏りが生じ、結果として顎関節に負担がかかることがあります。歯並びは見た目だけでなく、噛み合わせやあごの動きにも深く関係しており、歯並びが乱れていると、無意識のうちに顎関節に力がかかりやすくなるのです。
歯並びが与える影響
歯並びが乱れている状態では、上下の歯が正常に重なり合わず、顎関節に余計な負担がかかります。噛み合わせがあっていない状態で無理に噛み合わせようとすると、筋肉の緊張が生じます。顎関節に不自然な力が加わると、顎関節症のリスクが高まるでしょう。
また、前歯や一部の歯だけが極端に咬み合わない状態では、咀嚼が難しくなります。その結果、顎関節だけでなく胃腸の不調につながることもあります。
歯並びの状態は、発音にも影響を及ぼします。特に、前歯の噛み合わせや位置に問題があると、サ行やタ行などの音が出しにくくなります。舌の動きが制限されることで、不明瞭な発音になることもあります。
歯並び以外の要因
歯並びが整っていても顎関節症になる人もいれば、歯並びが悪くても顎関節症にならない人もいます。つまり、顎関節症の原因は必ずしも歯並びとは限りません。
例えば、顎関節症の原因としてストレスが挙げられます。ストレスが溜まると、無意識に歯ぎしりや食いしばりをするようになることが多いためです。
また、姿勢の悪さや睡眠不足もストレスにつながります。仕事などで長時間猫背のような姿勢で過ごすことが多い方などは、頸部や肩周りの筋肉が緊張し、顎関節症のリスクが高くなることがあります。睡眠不足が続くと自律神経のバランスが乱れるため、同様に顎関節症になるリスクが増します。
顎関節症の治療法
顎関節症の治療は、その原因や症状の程度に応じてさまざまなアプローチがあります。ここでは、具体的な治療法とその目的、患者さまの理解と協力の重要性について解説します。
薬物療法
顎関節症では、あごの痛みや違和感が生じることがあります。そのため、痛みがある場合は、痛み止めを処方するケースが多いです。
また、歯ぎしりや食いしばりが疑われる場合は、睡眠薬や抗うつ薬などを使用することもあります。不安感を軽減したり、睡眠の質を高めたりすることで、ストレスや歯ぎしり・食いしばりの軽減を目指します。
スプリント療法
顎関節症の治療で代表的なのが、スプリント療法です。専用のマウスピースを就寝時に装着することで、歯ぎしりや食いしばりによる関節への負担を軽減します。スプリントは個々の歯並びや噛み合わせに合わせて作成されるため、高い効果が期待できるでしょう。
理学療法
顎関節周囲の筋肉をほぐすためのマッサージや、関節の動きをスムーズにするためのストレッチなど、理学療法を取り入れるケースもあります。専門家の指導のもとで行うことで、筋肉の緊張を和らげ、痛みや開口障害の改善を目指します。
顎関節症を予防するためにできること
顎関節症は一度発症すると完治までに時間がかかることもあり、予防が非常に重要です。歯並びや顎の使い方、生活習慣の乱れなど、日々の積み重ねが予防のために欠かせません。
ここでは、どのような点に注意すればよいのかを具体的に解説していきます。
正しい噛み合わせを保つ
歯並びが悪く、上下の歯が正しく噛み合っていないと、顎関節に余分な力がかかりやすくなります。そのため、子どものうちから歯並びや噛み合わせを整えることが、将来の顎関節症予防につながります。
早期に相談すると、成長を利用した矯正治療が可能になる場合があります。
ストレスを軽減する
ストレスが溜まると無意識に歯を食いしばったり、片側だけで噛む癖が出たりすることがあります。これらの習慣は顎関節に不必要な負荷をかけるため、ストレスをコントロールし、心身をリラックスさせる習慣を持つことが予防にとって非常に有効です。
たとえば、仕事の合間に軽いストレッチをしたり、深呼吸や瞑想で心を落ち着けたりするなど、日常的にできるリフレッシュ方法を取り入れると良いでしょう。
マウスガードの使用
歯ぎしりが原因で顎関節症を発症している場合、就寝時にマウスガードを装着することで歯や顎関節への負担を軽減できます。口の開閉時に音がする、痛みがある、あごが疲れるといった症状がみられる場合も、マウスガードを使用することで症状の改善が期待できます。
偏った噛み癖を改善する
左右いずれか一方の歯で噛む癖は、顎関節に不均等な力をかけ続けます。長期的に力がかかると顎関節の位置がずれたり、周囲の筋肉が緊張して痛みが出たりする可能性があります。
左右でしっかり噛むことを習慣づけると、顎関節につく力を分散できます。食事の際に意識的に左右の歯を交互に使い、筋肉のバランスを整えると顎関節を正しい状態に保ちやすくなります。
顎の運動を取り入れる
日常生活のなかで、顎の関節を意識的に動かすことで、関節の柔軟性を保つ予防が期待できます。例えば、大きく口を開け閉めする、左右に動かす、舌を前後左右に動かす運動などが効果的です。
ただし、無理な動きはかえって悪化させる恐れがあるため、少しずつ行うようにしましょう。
就寝時の対策をする
寝ているときの姿勢や癖も顎関節に影響します。うつ伏せ寝は避け、横向きや仰向けで寝るようにしましょう。とくに、うつ伏せ寝は首や顎に負担をかける姿勢です。そのため、長時間この姿勢で寝ると、顎関節症を引き起こすことがあるでしょう。
また、硬すぎる床や枕の高さが合っていない状態も、顎に負担がかかる原因になります。顎を安定させる形状の枕を選んだり、マットレスや布団を適度な柔らかさ・弾力性のものにしたりすることで、顎関節症の予防につながります。
生活習慣を整える
顎関節症を予防するには、生活習慣を整えることも大切です。十分な睡眠を取り、疲労をためないよう心がけましょう。ストレスを完全に避けるのは難しいですが、ストレスがたまったら発散するようにしてください。
定期的に歯科検診を受ける
歯並びや噛み合わせの異常は、日常生活では気づきにくいことが多くあります。
しかし、歯科医院での定期的なチェックを受けることで、問題の早期発見・早期治療が可能になります。小さな歯列不正や顎関節の軽いズレでも、歯科医師の目から見れば、将来的な顎関節症のリスクを判断できる場合があります。
痛みや不調がなくても、歯やあごの状態を確認するために定期検診を受けるようにしましょう。
まとめ
顎関節症は、痛みや不快感などのつらい症状だけでなく、食事や会話といった日常生活にも影響を及ぼす可能性があります。
顎関節症の原因のひとつに歯並びの乱れがあることは確かです。歯並びや噛み合わせの異常がある場合、顎関節に負担がかかるため、顎関節症になるリスクが高くなります。
ただし、顎関節症の原因は、歯並びだけではありません。ストレスや生活習慣など、さまざまな要因が関係しているため、歯並びだけを改善すればよいというものではないのです。顎関節症の予防には、さまざまな角度からのアプローチが必要になります。
歯並びの改善や顎関節症の治療を検討されている方は、兵庫県西宮市にある医療法人社団 西宮北口ライフ歯科・矯正歯科・小児歯科にご相談ください。
当院では、小児矯正・成人矯正をはじめ、虫歯治療や歯周病治療、マタニティ歯科、ホワイトニングなどにも力を入れています。ホームページはこちら、WEB予約やLINE予約相談もお受けしておりますので、ぜひご覧ください。
小道俊吾